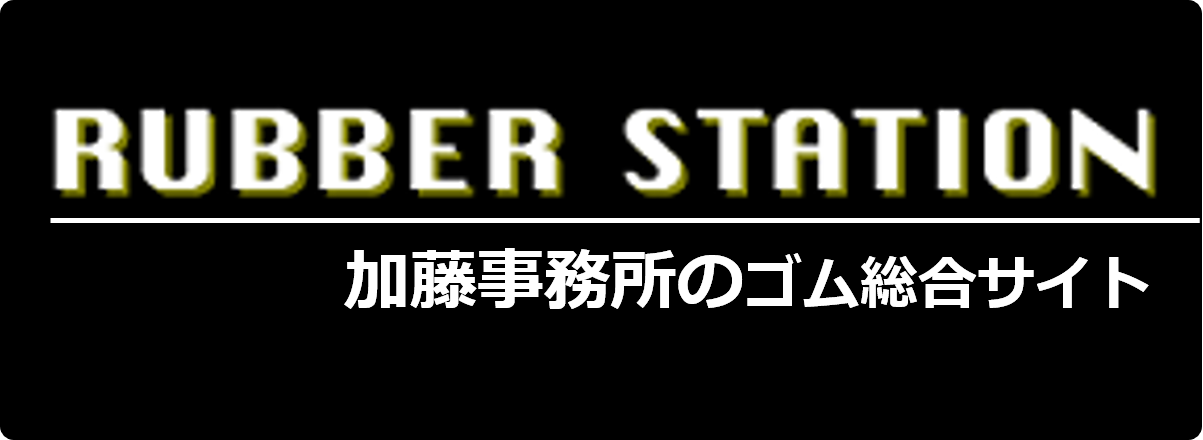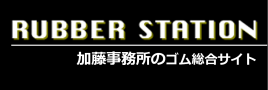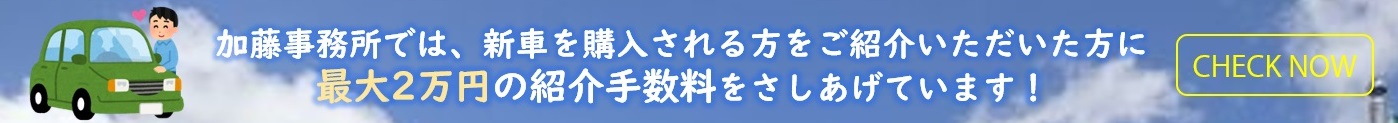<日産自動車>
「日産自動車“静かなる解体”――本社売却、工場閉鎖、赤字7,500億円果てに・・・」
ルノーとの蜜月解消から始まった転落のカウントダウン
4月2日、日産とルノーの相互出資比率が15%から10%に引き下げられると発表された。ルノーのEV子会社「アンペア」への出資も撤回し、インド合弁会社株式の売却で620億円を確保。さらにルノー株の一部売却で最大1,100億円の資金を得られる体制を整えた。表向きは「経営の機動力向上」だが、業界関係者は「これは資産現金化の第一弾にすぎない」と語る。
史上最大の赤字、工場の稼働率は半分以下
4月25日、日産は2025年3月期の最終赤字見通しを7,500億円と公表。米国・中国・日本の主要工場稼働率は軒並み50%台に低迷し、損益分岐点の8割を大きく下回る。世界販売台数は335万台と前年から3%減少、計画も下方修正された。「稼働率の数字を見た瞬間、現場は凍りついた」(国内工場関係者)
縮小路線へ急ハンドル
5月14日には、国内外17工場のうち7工場を削減し、10工場体制へ移行する計画が浮上。5月18日にはメキシコ、南アフリカ、インド、アルゼンチンの工場閉鎖案も判明。2027年度には世界生産台数を250万台にまで削る方針が固まった。
本社売却と資金繰りの綱渡り
5月24日、日産本社ビル(資産価値1,000億円超)の売却検討が明らかに。目的はリストラ費の捻出だ。同時期にルノー株5%(約1,000億円分)を売却し、さらに英国政府系の保証を利用して2,000億円の融資も検討中。2026年3月期に控える最大6,000億円規模の社債借り換えが背景にある。
追浜工場をめぐる幻の“鴻海連合”
7月7日、台湾・鴻海精密工業とEV生産協議に入ったとの報が流れ、追浜工場(年産能力24万台)の共同利用案が浮上。だが7月16日、日産は追浜工場の2027年度末での生産終了を正式発表。湘南工場も26年度末で閉鎖される。国内完成車工場は5か所から3か所へ。
「希望は3週間しか持たなかった」と、地元関係者は肩を落とす。
販売不振と続く赤字地獄
7月31日、4〜6月期決算で最終赤字1,157億円と発表。これで4四半期連続の赤字だ。中国販売は前年同期比28%減、米国7%減、日本11%減と全方位で低迷。販売計画325万台は据え置かれたが、達成は極めて厳しい情勢だ。
「これは改革ではない、撤退戦だ」
ルノーとの関係見直しに始まり、本社売却、工場閉鎖、資産現金化、そして巨額赤字――。わずか4か月の間に日産は、企業規模を大幅に縮小する方向へ急旋回した。ある元幹部はこう断じる。
「これは再建ではない。生き残るための分解だ」
2027年、追浜工場のシャッターが下ろされる日。日産の看板は、どこに残っているのだろうか。
<トヨタ自動車>
「トヨタ、“世界覇権”死守の逆襲――創業家回帰、巨額買収、EV包囲網の全貌」
上海にレクサス拠点――中国本土での攻防開始
4月18日、トヨタ自動車が中国・上海市に260億円を投じ、レクサス専用の工場用地を確保したことが明らかになった。使用期限は50年、生産能力は年間10万台規模。稼働開始は2027年以降で、新たに1,000人を雇用する計画だ。
4月27日には中国市場で新型SUV「bZ3X」の販売価格を10万9,800元に設定し、ライバルのホンダ(P7)を大幅に下回る攻勢を開始。世界最大市場での価格競争に真正面から挑む姿勢を鮮明にした。
国産300万台死守の執念
5月9日、国内生産323万台体制の維持を宣言。米国市場への輸出が全体の3割弱を占め、中国向けは10%。世界販売の柱は依然として日本・米国・中国の三極構造だが、現地化の圧力は強まる一方だ。
創業家回帰の衝撃――4.7兆円TOB
6月4〜5日、グループ源流の豊田自動織機が4兆7,000億円で株式非公開化される計画が発表された。買収主体はトヨタ不動産と豊田章男会長による持株会社。この動きは、戦後初ともいえる「創業家主導の再集結」として業界を震撼させた。関係者は「グループ再編はこれで終わらない」と語る。
日野と三菱ふそう、異例の統合
6月11日、トヨタ傘下の日野自動車とダイムラー傘下の三菱ふそうが経営統合で最終合意。中国メーカーの台頭とEVシフトの加速が背景にある。世界商用車市場での再編の波は、もはや不可逆だ。
インドネシア・チェコ…EV戦線拡大
7月24日、トヨタはインドネシアで年内にEV「bZ4X」を生産すると発表。中国勢が攻勢を強める市場でシェア首位を死守する狙いだ。
7月30日には、2028年にもチェコで欧州初のEV現地生産に踏み切る方針が判明。環境規制の厳しい欧州市場で、14車種のEV投入計画を進める。
世界1,000万台生産の野望
8月2日、2025年の世界生産台数を1,000万台規模とする計画が浮上。26年には1,020万台、27年には1,050万台を見込む。上期だけで過去最高の491万台を記録し、ハイブリッド車の好調が押し上げた。
タイでの中国部品調達と牙城崩壊の兆し
8月3日、トヨタがタイで低コストEV・HVのために中国製部品を調達する方針が明らかに。かつて新車販売の9割を日本勢が占めたタイ市場も、中国BYDなどの台頭で日本車シェアは71%まで低下。価格競争の波が、東南アジアの“安住の地”を侵食し始めている。
「攻め」と「守り」の境界線
上海からチェコ、インドネシア、タイまで――トヨタは世界各地で次々と布陣を組み直している。その一方で、創業家回帰という歴史的再編に踏み切り、グループ全体を戦時体制に近い形で再構築中だ。 業界関係者は言う。
「トヨタは攻め続ける限り強い。しかし、それは常に崖っぷちの戦いだ」
1,000万台という数字の裏にあるのは、世界規模の覇権争奪戦の最前線だった――。
<その他日系自動車メーカー>
「関税ショックで揺らぐ牙城――日本車メーカー、総力防衛戦」
鴻海に頼る三菱自の苦渋
5月7日、三菱自動車は台湾の鴻海(ホンハイ精密工業からEVを調達し、2026年後半からオーストラリア・ニュージーランド市場で販売すると発表した。EVの自社開発に巨額投資を回せない中、外部調達で時間を稼ぐ狙いだが、「三菱ブランドの独自性が薄まる」との懸念も業界内には根強い。さらに6月26日には、鴻海製のEVバスやマイクロバスを三菱ふそうブランドで販売する方向も判明。商用車分野でも“外注依存”の色が濃くなる。
ホンダ、インドに活路
5月23日、ホンダはインド西部グジャラート州の第4二輪車工場に約160億円を投じ、65万台の増産を計画。稼働すれば世界最大級の二輪工場となる。国内市場の9%成長と、世界生産の3割を占めるインドの需要を背景に、二輪部門での稼ぎを強化する構えだ。
日産と“復縁”を探るホンダ
6月20日、ホンダは株主総会で、日産自動車との協業を検討中であると公表。4か月前に白紙となった経営統合の再接近の背景には、米国の輸入車関税25%がある。ホンダは純利益7割減の見通し、日産も最大4,500億円減益要因を抱え、互いに米市場でのコスト削減が急務。
「仲直りのきっかけは、トランプの関税」と関係者は語る。
スバル、“ドル箱”米国に賭ける
同じく関税直撃を受けるのがスバルだ。米国販売比率71%という高依存体質は、営業利益3,600億円が一撃で吹き飛ぶリスクをはらむ。6月26日の株主総会では、秋から米インディアナ工場で新型フォレスターの現地生産を開始し、年40万台超への増強を計画。まさに“フォレスター頼み”の勝負に出た。
ホンダ、戦略EV撤退の衝撃
7月6日、ホンダは大型SUVタイプの戦略EV開発を中止。米国での需要減に加え、EV購入補助金の打ち切りが決定し、ハイブリッドシフトへ急転換する。
関税に泣くマツダ
8月6日、マツダは4〜6月期で421億円の赤字を計上。米国向け輸入比率8割の体質が災いし、関税影響だけで697億円の営業減益。米市場依存の危うさが数字で露呈した。
スズキ、インド頼みが失速
同日発表されたスズキの4〜6月期決算も純利益11%減。世界販売は5年ぶりに減少し、稼ぎ頭のインド市場で6%減を記録。欧州販売も27%減と二正面で苦戦した。
総評――「関税恐慌」下の生存戦略
米国の関税25%は、日本車メーカーの収益構造を直撃。各社は現地生産の加速、他社との協業、外部調達など手段を問わず生き残りを図っている。しかし、その動きは「自主独立の終焉」とも映る。ある業界アナリストはこう警鐘を鳴らす。
「このままでは、日本車ブランドは“現地メーカーの一部門”になりかねない」
関税の壁の向こうで、彼らの戦いはすでに始まっている――。